長い妊娠期間を経てやっと会えた我が子。本当に愛おしくて、かけがえのない大切な存在ですよね。
初めての育児は幸せいっぱいですが、その一方で、初めてだからこその不安や戸惑いも多いもの。
オムツ替えやお風呂の入れ方、授乳の方法など、産院で教わったことを思い出しながらも、自宅に戻ると「これで合っているのかな?」と悩むことが多いのではないでしょうか。
たとえば「寝不足が続いて疲れが取れない」「授乳がうまくいかない」など、新生児期ならではの悩みがつきものです。
この記事では、新生児期によくあるお悩みとその対策、ママの心が少しでも楽になる考え方のヒントをご紹介します。安心して育児を楽しめるように、お手伝いができれば幸いです。
何をやっても泣き止まない、なかなか寝ない。
赤ちゃんは泣くのが仕事。そうわかっていても、泣き続ける我が子を見ていると辛くなり、なんとかして泣き止ませたいと思ってしまいますよね。
オムツを替えて、ミルクをあげて、抱っこして…できることは全部やったのに、それでも泣き止まない。なぜ泣いているのかわからず、途方に暮れてしまい、ついこっちまで泣きたくなることもあると思います。
私も赤ちゃんと一緒に泣いたことが何度もあります!
そんな時に、これを知っているだけで、少し気持ちが楽になるかもしれません。
メンタルリープ
メンタルリープとは、赤ちゃんの脳が急激に成長するタイミングのことを指します。
生後20ヶ月までに約10回起こると言われており、この成長の過程で赤ちゃんが敏感になり、赤ちゃんがいつもより泣いたり、ぐっすり眠れなかったりすることが多くなります。
もし「何をしても泣き止まない!」という状況が続いていたら、それはメンタルリープのせいかもしれません。
赤ちゃんの脳が急成長している証拠なんです。
このことを知っているだけでも、「泣き止まないのは私のせいじゃない」と思えるようになり、少し気持ちが楽になるのではないでしょうか?
快適なお部屋づくり


加湿器や空気清浄機
赤ちゃんは体温調整がまだ苦手なので、快適な温度や湿度に整えてあげることが大切です。
室温や湿度が適切でないと、赤ちゃんが眠りづらくなり、頻繁に起きてしまう原因になることもあります。
赤ちゃんの様子をよく観察しながら、温度や湿度を調整してあげましょう。
その際、エアコンやヒーターの風が直接当たらないよう注意することもポイントです。
加湿器や空気清浄機を活用すれば、部屋の空気を快適に保ち、赤ちゃんにとってより安心できる環境を作ることができます。
メリーやモビール
赤ちゃんは生後2〜3ヶ月頃から、動くものを目で追うようになり、色や形を少しずつ認識しはじめます。
視覚的な刺激は、赤ちゃんの五感を刺激し、心身の成長や脳の発達を促すと言われています。
メリーによくある「オルゴール音楽」も、寝かしつけや泣き止ませる効果が期待できる便利な機能です。
それだけでなく、優しい音楽はママにとってもヒーリング効果があり、育児中のリラックスタイムとしてもおすすめです。
メリーやモビールを取り入れて、赤ちゃんとママのリラックスタイムを過ごしましょう。
ベビーモニター
やっと泣き止んで寝たのはいいけれど、赤ちゃんの様子が気になってそーっとドアを開けたら起きてしまった…
そんな経験はありませんか?そんな時におすすめなのがベビーモニターです。
我が家では、末っ子が生まれてから現在3歳になるまで毎日使っています。赤ちゃんの様子を見守れるので、安心して家事をしたり、貴重な1人時間を過ごすことができます。
赤ちゃんの安全を確保しつつ、ママやパパの負担を軽減してくれる便利なアイテムです。ぜひ参考にしてみてください。
授乳中のトラブル
授乳に関する悩みは人によってさまざまです。「うまく授乳ができない」「母乳の量が足りない気がする」「傷ができて痛い」など。
私自身、一度「白斑」ができたことがあり、授乳のたびに激痛との戦いでした。白斑とは、乳管が詰まって栓のようになってしまう状態のことです。
初めは原因がわからず、ただ痛みに耐える日々。助産師さんに相談し、マッサージを受けましたがすぐには改善されませんでした。
そんな中、「白斑は授乳を続けることで治ることが多い」と教えてもらい、痛みに耐えながら授乳を続けた結果、気が付くと改善していました。
授乳中のトラブルに悩んでいる方は、まずは産院の母乳外来や助産師さんに相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、少しでも不安が軽減されるかもしれません。
授乳中に切なくなる
D-MER(ディーマー・不快性射乳反射)を知っていますか?
赤ちゃんが母乳を飲み始めると、なんだか切ない気持ちになったり、不快でネガティブな感情に襲われることです。
原因は解明されていませんが、射乳反射の変わったかたちではないかと考えられています。
人によって感じ方に違いはあるかもしれませんが、もし授乳中に「気持ち悪い」「イライラする」「泣きたくなる」などの気持ちに襲われたら、それはD-MERかもしれません。
私の場合、授乳中にホームシックになったかのような切ない気持ちになっていました。頻繁になるので、調べてみたらD-MERだとわかり、納得しました。
「幸せなはずの授乳中にこんなことを思う私は母親失格だ」なんて、決して思わないでくださいね。
生理現象なので、異常でも病気でもありません。
あると便利なアイテム
授乳クッション
授乳時の姿勢をサポートしてくれる授乳クッションは、育児中の必需品です。
赤ちゃんをちょうど良い高さに支えてくれるので、ママの肩や腰への負担を軽減し、授乳中の疲れを軽くしてくれます。
さらに、授乳だけでなく、赤ちゃんのクッションとしても大活躍します。
赤ちゃんを寝かせたり、お座りの練習をサポートしたりする時にも使えます。用途が幅広いので、赤ちゃんが成長しても長く使えるのが嬉しいポイントです。
洗えるカバー付きや、コンパクトに収納できるタイプなど、さまざまなデザインが販売されています。お好みのデザインや素材を選べるのが嬉しいですね。
搾乳機
搾乳機は、母乳育児を続けるうえで心強い味方です。
授乳中に傷ができて痛いときや、外出先で授乳が難しい時、赤ちゃんを誰かに預ける必要がある時など、さまざまな場面で役立ちます。
搾乳した母乳は冷蔵または冷凍保存しておくことで、必要な時に赤ちゃんに与えられるため、育児の選択肢が広がります。
搾乳機を選ぶ際は、使う頻度やライフスタイルに合わせて検討しましょう。
また、搾乳後の母乳を保存するための専用パックやボトルもあわせて準備しておくと便利です。
搾乳機には2種類のタイプがあります。
・手動タイプ:手軽で持ち運びやすく、外出時や使用頻度が少ない場合におすすめです。
・電動タイプ:効率的に搾乳できるため、頻繁に搾乳が必要な場合や、短時間で済ませたい時に便利です。
特に電動タイプは、両胸同時に搾乳できるモデルもあり、忙しいママにぴったりです。
保護クリーム
授乳中に傷ついた乳頭をケアするための必須アイテムが、保護クリームです。
授乳中は頻繁な吸引によって乳頭がダメージを受けやすく、ひび割れや痛みが生じることもあります。
そんな時、保護クリームを使うことで乳頭をしっかり保湿し、ダメージの回復をサポートします。
保護クリームの多くは、赤ちゃんの口に入っても安全な成分で作られているため、塗ったあとにふき取る必要がなく、そのまま授乳が可能です。
また、保護クリームは乳頭ケアだけでなく、赤ちゃんのスキンケアにも使える万能アイテムです。
製品によっては携帯サイズのものもあり、外出先でのケアにも便利です。
母乳パッド
母乳パッドは、母乳育児をしているママにとって欠かせないアイテムです。
母乳漏れを防ぎ、衣類を清潔に保つ役割を果たしてくれるため、特に授乳の頻度が高い新生児期には重宝します。
外出中や夜間の母乳漏れが気になる時にも安心して過ごせます。
母乳パッドを選ぶ際は、吸収力や肌触り、自分のライフスタイルに合ったものを選ぶことがポイントです。
また、母乳パッドの装着部分がズレにくいものを選ぶと、より快適に使用できます。
母乳パッドには2種類のタイプがあります。
• 使い捨てタイプ:吸収力が高く、外出先や忙しい時に便利です。使用後にそのまま捨てられるので衛生的で手軽に使えます。
• 布製タイプ:繰り返し使えるため経済的で、環境にも優しい選択肢です。柔らかい素材のものが多く、肌が敏感なママにもおすすめです。
哺乳瓶
授乳が難しい時や外出時に活躍するだけでなく、ミルクを足したり、母乳をやめてミルクだけに切り替えるのも選択肢のひとつです。
育児に正解はなく、ママ自身を大切にすることが育児を楽しむ鍵です。
赤ちゃんのためにも、ママに合った方法を選びましょう。
哺乳瓶の種類。
・ガラス製:傷がつきにくくて衛生的。熱伝導率が高いので、早く冷めて授乳がスムーズ。授乳頻度は高い方におすすめです。
・プラスチック製:軽くて割れにくい。お出かけの時に便利です。プラスチック製の中でも、ガラスのような新しいプラスチック素材が使われているものもあります。
哺乳瓶の種類が多くて選べない場合は、産院で使っていたものと同じ哺乳瓶を選ぶのもおすすめです。
私も実際に、出産した産院で購入できた哺乳瓶をそのまま退院時に購入しました。自宅に帰ってからすぐに使えたので、とても助かりました。産院で使用しているものなら、赤ちゃんも慣れていて安心です。
お出かけに便利なアイテム


生後1ヶ月の健診で問題なければ、赤ちゃんと一緒に外気浴をしたり、近所のスーパーに買い物に出かけたりしたくなりますよね。
でも「初めての外出は不安…」という方も多いのではないでしょうか。
そんな時に役立つ、お出かけ時にあれば便利なおすすめアイテムをご紹介します。
抱っこ紐やスリング
お出かけの際にベビーカーを使うことが多いかもしれませんが、赤ちゃんが突然泣き出して抱っこが必要になる場面も少なくありません。
そんな時に役立つのが抱っこ紐やスリングです。
抱っこ紐やスリングを使うことで、赤ちゃんを抱っこしながらも両手が使えるため、外出時や家事をする時に便利です。
赤ちゃんもママの体温や心臓の音を感じることで安心感を得られ、落ち着いて過ごすことができます。
抱っこ紐やスリングを選ぶ際には、装着のしやすさやママやパパの体型に合っているかが重要です。
通気性の良い素材や、肩や腰への負担を軽減するクッション付きのものなど、多様なタイプが販売されているので、ライフスタイルに合ったものを選びましょう。
抱っこ紐とスリングの違い
• 抱っこ紐は、安定感があり、赤ちゃんを長時間抱っこする時に最適です。前向き抱っこやおんぶなど、さまざまなポジションに対応できるタイプが多く、ママの体にフィットするため、肩や腰の負担が軽減される工夫が施されています。
• スリングは、軽量でコンパクトに収納できるのが特徴。短時間の使用や新生児の抱っこに適しており、装着も比較的簡単です。赤ちゃんを包み込むように抱っこできるため、密着感が高く安心感があります。
着替え
短時間の外出でも、オムツ漏れや吐き戻し、汗などで服が汚れることはよくあります。
赤ちゃんとのお出かけには、着替えを1セット以上用意しておくと、万が一の時にも慌てずに対応できるので安心です。
外出先では荷物を減らしたいので、小さく畳める素材の服を選ぶと便利です。
また、汚れた服を入れるためのビニール袋や防臭袋をバッグに入れておくと更に安心です。
ガーゼブランケット
ガーゼ素材のブランケットは軽くてかさばらないため、一枚バッグに入れておくだけで、赤ちゃんとのお出かけ時に大活躍します。
柔らかく通気性が良いので、季節を問わず一年中使える便利なアイテムです。
赤ちゃんの肌に優しいだけでなく、使い道が幅広いことが魅力です。デザインや柄も豊富なので、好みに合わせて選ぶ楽しさもあります。
ガーゼブランケットの活用シーン
• 赤ちゃんが寝た時の掛け物に
• オムツ替えの敷物として
• 授乳時の目隠しに
とにかく寝たい


月齢の低い赤ちゃんは、まだまとまって長く寝ることが難しく、2~3時間おきに授乳やオムツ替えが必要になります。
その結果、ママはどうしても睡眠不足になりがちです。
赤ちゃんは可愛くてお世話も楽しいけれど、睡眠不足が続くと体力も気力も消耗し、思考力が低下してしまいます。
そんな状態では心が不安定になり、赤ちゃんのことを「可愛い」と思えなくなる瞬間が出てきてしまうかもしれません。
もし近くに頼れる家族や友人がいるなら、育児のことを相談したり、少しの間赤ちゃんを見てもらい、その間に短時間でも休息を取りましょう。
自治体のサポートを調べてみよう
昼間は赤ちゃんと2人きりで、周りに頼れる人もいない。
そんな時は自治体のサポート制度や家事代行サービスを活用するのも一つの選択肢です。
自治体によっては、家事育児支援やベビーシッターサービス、育児相談窓口など、さまざまな支援制度を提供しています。
まずはお住まいの自治体がどのようなサービスを提供しているかを調べてみましょう。
「サービスを使うのは気が引ける…」と思う方もいるかもしれませんが、楽しいはずの育児が「辛い」「しんどい」と感じるものにならないためにも、利用できるサポートは積極的に取り入れるべきだと思います。
サービスを使うのもひとつの手
家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用することは、何も後ろめたいことではありません。
ママは出産という人生の一大イベントを終え、体も心も大きなダメージを受けています。
妊娠と出産はあっという間ですが、これから始まる育児は長い道のりです。
特に体が回復途中のこの短期間だけでも、周囲やサービスに頼ることは大切です。ママの心と体を守るために、必要なサポートを積極的に活用してみましょう。
まとめ
育児の中でも、特に悩みが多いのがこの新生児期ではないでしょうか。
初めての出産や育児となると、何もかもが初めてで戸惑うことばかりですよね。
周りに相談できる家族や先輩ママがいれば心強いですが、そうでない場合もあるかと思います。
ネットも便利ですが、多くの意見がある中で、すべてを鵜呑みにするのではなく、自分に合った情報を選び取ることが大切です。
子育てに正解はありません。
私自身、4人の子育てをする中でさまざまな悩みに直面しましたが、自分で調べたり、周囲に相談したりしながら、自分に合った方法やアイテムを取り入れるようにしています。
今回は生後0〜3ヶ月のよくあるお悩みについてお話しました。
これからも年代ごとの悩みについて記事を更新していく予定です。少しでも誰かの助けになれば幸いです。
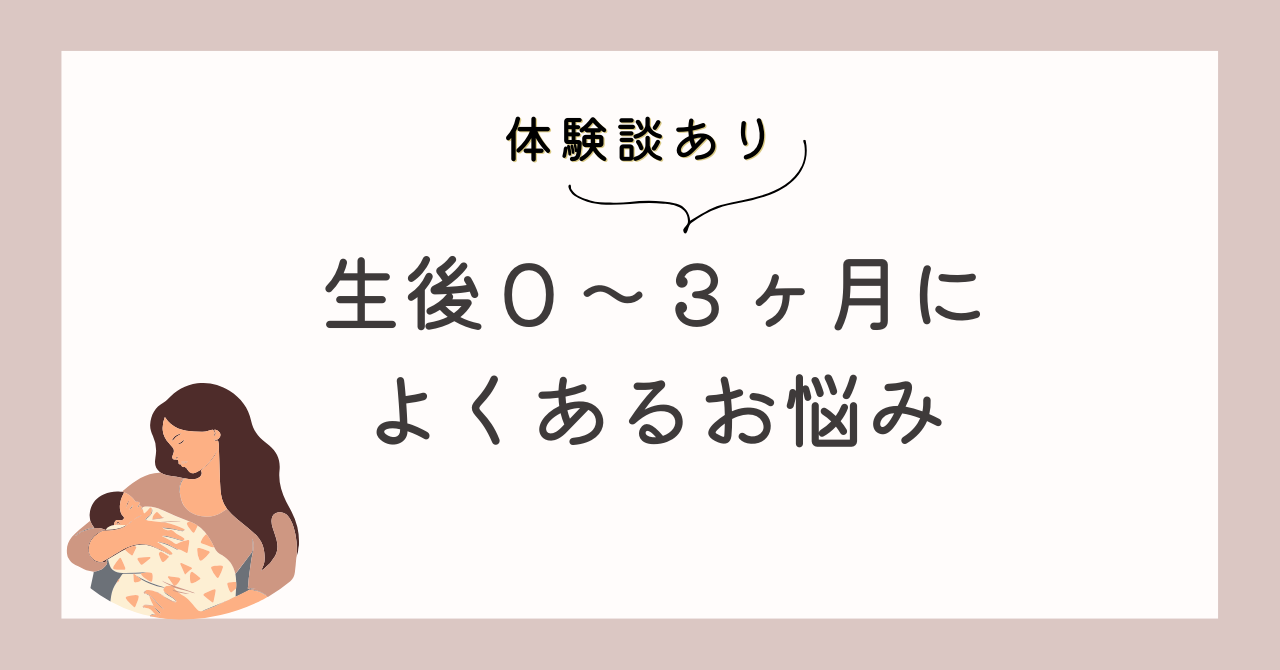
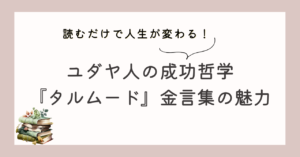
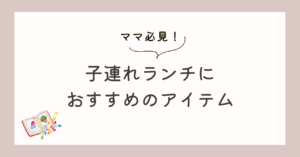
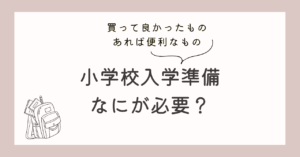
コメント